世代間で変わるオタク活動のスタイル
こんにちは。40代独身オタク兼FP(ファイナンシャル・プランナー)のシュンキャンです。
ここ数年、アニメやゲームのイベントに参加していると、「あ、これ世代ごとに楽しみ方が違うな」と感じることが増えました。同じ推しを応援していても、SNSでの発信の仕方、グッズの買い方、遠征のスタイルまで、世代によってかなり異なります。
今の私は、ちょっと良いホテルに泊まり、美味しいご飯もついでに楽しむ遠征が増えました。これは単なる“贅沢になった”ではなく、世代による価値観やライフスタイルの変化が大きいんですよね。
今回は、10代から40代以上までの世代別オタク活動の特徴と、その背景、そして世代差を楽しむコツをお話しします。
■ 世代別オタク活動の特徴
| 世代 | 主な情報源 | 活動スタイル | お金の使い方 | 人との交流 |
|---|---|---|---|---|
| 10代〜20代前半 | TikTok・Instagram・X | SNS発信重視、映えを意識 | 予算は少ないがグッズや推し変も柔軟 | オンライン中心で友達作り |
| 20代後半〜30代 | X・YouTube・配信サービス | 仕事と両立、イベント参加は厳選 | 収入増で遠征や良席チケットに投資 | 小規模で濃い交流 |
| 40代以降 | X・公式サイト・口コミ | 計画的遠征、体験優先 | 限定グッズやプレミア体験に投資 | 少人数またはROM専気味 |
■ 10代〜20代前半
この世代はSNSネイティブ。特にTikTokやInstagramでの「映え」が重要で、イベント参加も“現地で楽しむ”のと同じくらい“どう発信するか”がポイントになっています。推し変や掛け持ちも柔軟で、流行に乗るスピードが速いのも特徴です。
私から見ると、このフットワークの軽さと情報収集能力はうらやましい限り。ただ、予算は限られるため、夜行バスや格安宿泊など、コストを抑える工夫が必須です。
■ 20代後半〜30代
仕事が生活の中心になり始める時期。時間の自由は減りますが、その分収入が増えて、チケットや遠征の選択肢が広がります。「行けるイベントは厳選して、確実に楽しむ」というスタンスが多くなります。
ホテルも快適さ重視になり、現地での食事も少し豪華に。交流も、SNSの広い人脈よりも、信頼できる小さなグループとの濃いつながりを大切にする傾向があります。
■ 40代以降
体力と時間の配分を意識するようになり、「行きたいイベント全部!」というよりは、特に思い入れのある現場を優先します。遠征は綿密に計画し、有給をきちんと確保。ホテルは立地と静かさ重視で、移動も快適さ優先になります。
また、この世代はグッズよりも“体験”にお金を使う傾向が強まります。良席チケット、プレミアイベント、少人数トークショーなど、「一生の思い出になる時間」に投資します。
■ 世代差が生まれる理由
- SNS文化の変化
私の若い頃は、mixiの日記や個人ブログが中心でした。今は、写真や短い動画で一瞬にして情報を発信できる時代。発信がリアルタイム化したことで、現地での行動や持ち物も変わりました。 - ライフステージの違い
学生は時間がある代わりにお金がない。社会人はお金がある代わりに時間がない。中高年はお金はあるけど体力が減る――この三すくみ状態が活動スタイルを分けます。 - 経済状況の差
推し活費用は、物価感覚や生活費の余裕にも影響されます。たとえば「グッズは全部買う派」か「厳選して買う派」かは、世代や生活の安定度によって変わります。
■ 世代間ギャップを楽しむコツ
- 観察を楽しむ:若い世代の行動は、自分にはない発想やスピード感があって面白い。「こういう文化もあるのか」と研究する気持ちで見ると、違いがストレスではなく刺激になります。
- 経験で貢献する:チケット取得のコツや遠征計画の立て方など、経験から得た知識は若い世代にとって貴重です。
- 共通の話題を持つ:世代が違っても、作品の深い考察や推しの魅力語りは盛り上がれるテーマ。逆に流行語やSNS文化の細かいところに無理に合わせなくてもOKです。
- 無理に合わせない:オタ活は「マイペースが正解」。体力や生活リズムに合った楽しみ方をすることが長く続けるコツです。
■ まとめ
世代ごとのオタク活動の違いは、ギャップというより多様性。同じ作品や推しを応援していても、そのアプローチや熱量の形は様々です。だからこそ、世代を超えて同じ空間を共有できるのは面白いことだと思います。
自分の世代の強みを活かしつつ、推し活を長く続けられるスタイルを見つけていきましょう。
それでは今回はこのへんで。
また次の記事でお会いしましょう!
— シュンキャン

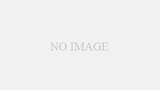
コメント