「推し」なんて言葉はなかった——90年代・00年代、“ひとりオタク”のリアル
こんにちは。40代独身オタク兼FP(ファイナンシャル・プランナー)のシュンキャンです。
今は「推し活」という言葉がすっかり定着し、SNSやイベントで“好き”を共有するのが当たり前の時代。でも、私たちが青春時代を過ごした90年代〜00年代は、そんな空気ではありませんでした。
「オタク=変わり者」と見なされ、好きな気持ちは隠すもの。誰にも言えないけど、確かに心の中に“好き”があった——。
今回は、そんな“ひとりオタク時代”のリアルを、今あらためて振り返ってみたいと思います。
【90年代】“好き”を語れない時代
今のようにオタク文化が表に出てくることはほとんどなく、アニメやゲームが好きだと堂々と言える雰囲気はありませんでした。
情報源は本・テレビ・ラジオだけ
- アニメ誌(ニュータイプ、アニメディアなど)をこっそり購入して、部屋で熟読
- 深夜アニメはVHSで録画し、家族が寝たあとに一人で再生
- 声優さんのラジオ番組をカセットに録音して繰り返し聴く
- 新作情報は雑誌の巻末やテレビの番組表を頼りにチェック
今のようにネットで即座に情報を得られる時代ではなく、ひとつの特集や一言コメントが何度も読み返される貴重な情報源でした。
お店で買うのも一苦労
アニメイトや本屋でグッズや本を買うときは、誰かに見られないように時間帯や店舗を選んでいました。「クラスメイトに見られたらどうしよう…」という緊張感が常にあって、買い物ですら一大ミッション。
「推し」ではなく“ただただ好きなキャラ”
「推し」なんて言葉は存在しませんでしたが、心の中では「このキャラのことが本当に好き」と強く思っていました。誰にも言えず、ただひたすら、ひとりで想いを育てていた。そんな静かな情熱が、自分の中で何よりも大切だったのです。
【00年代】ネットはあっても“語らない”オタク
2000年代に入り、ようやく家にインターネットが導入されました。けれども当時は、今のようなSNSもなく、情報を探して静かに楽しむ「見る専」スタイルが主流でした。
ファンサイトを巡って静かに共感
イラストサイトや考察ページをブックマークして、更新されるたびにチェック。でも掲示板に書き込む勇気はなく、コメントも残さず、ただ眺めては「自分と同じ気持ちの人がいる」と感じて満足していました。
“ひとりきりのオタ活”に没頭する日々
好きなアニメを繰り返し観て、グッズをこっそり飾って、雑誌を切り抜いてノートに貼る。語らずとも心は満たされていた。外に向けるより、自分の中でじっくり味わう“オタ活”が、あの時代のスタイルでした。
そして今、「推し活」ができる幸せな時代
今ではSNSで「推し」について熱く語り、イベントで仲間と盛り上がれる。本当に素敵な時代になったと思います。
けれど、あの頃の誰にも言えなかった“好き”も、私にとってはかけがえのない時間でした。言葉がなくても、誰かと共有できなくても、作品とまっすぐに向き合い、自分の中で感情を育てていたあの頃の自分——それが、今の私の「好きの原点」になっているのです。
孤独だったけど、熱量は本物だった
「推し」という言葉はなかったけれど、SNSも、語る場所もなかったけれど、私たちは確かに、強く深く“好き”を持っていた。
あの頃の“ひとりオタク”だった自分を、今はちょっと誇りに思っています。そしてこれからも、あの熱量を忘れずに、“推し活”を楽しんでいきたいと思います。
それでは今回はこのへんで。
また次の記事でお会いしましょう!
— シュンキャン

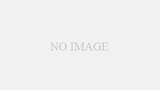
コメント