こんにちは。40代独身オタク兼FP(ファイナンシャル・プランナー)のシュンキャンです。
推しが新作グッズを出せば即ポチ、予約特典違いで全種買い、イベント現地限定も「行けるなら全部」――その情熱、痛いほどわかります。
ただし、「愛は無限でも、財布は有限」。長く推しを応援し続けるためには、“推し費”にライフプラン的な視点を入れることが不可欠です。
今回は、オタク兼FPとして、「推しグッズ購入」と「お金」のバランスをどうとるかについて、具体的に解説していきます。
1. まずは現状把握:「私、いくら推しに使ってるの?」
1-1. “思い出せる範囲”では足りない
「だいたい月○万円かな?」という“体感”は、たいてい下振れします。まずは直近3〜6か月のカード明細・通販履歴・レシートを洗い出してみましょう。
1-2. 支出は“定期型”と“突発型”に分ける
- 定期型:月刊誌、ファンクラブ会費、サブスクなど
- 突発型:受注グッズ、現場グッズ、大型イベント、円盤特典など
→定期型は「固定費」として把握、突発型は「推し貯金」から捻出するのが理想です。
2. 推し費の位置づけ:FP的に見る支出の分類
2-1. 支出の4分類
FPの基本的な考え方として、支出は以下の4つに分類できます。
- 固定費(家賃・通信費など)
- 変動費(食費・雑費など)
- 自己投資(資格・健康・学び)
- 浪費(娯楽・嗜好品など)
推し活は浪費に見えがちですが、精神的満足や創作意欲に繋がるなら「自己投資」とも言えます。
2-2. 「推し費」は独立させて管理
生活費・貯蓄・推し費を分けることで、無理のない範囲で推し活を楽しむ仕組みが作れます。
3. “推し費枠”を決める:目安と管理法
3-1. 月収に応じた目安
目安は手取りの5~15%。例えば手取り25万円なら、月1.25〜3.75万円がひとつの目安です。
3-2. 年間で考えるのもアリ
突発的なイベントに備えて、毎月1万円ずつ「推し貯金」する方法もおすすめです。年間12万円の“推し費用”を確保できます。
4. 優先順位をつけよう:「全部買う」は卒業
4-1. 満足度 × 再入手可能性
推しアイテムを「満足度」と「レア度(再販可能性)」の2軸で考えて、買う/我慢するを判断しましょう。
4-2. お金を使わない推し活もある
- SNSでの布教や感想
- 創作活動
- 配信視聴・拡散
“金銭的な支援”以外にも推しを応援する方法はたくさんあります。
5. 自分を守るための“仕組み化”を
5-1. 推し貯金を自動化
給料日に自動で積立する仕組みを作りましょう。目的別口座が使えるネット銀行が便利です。
5-2. 家計簿アプリで推し費をタグ管理
MoneyForwardやZaimなどで「#推し費」タグをつければ、毎月の支出が可視化できます。
5-3. 上限を超えたらストップ
「今月は予算を使い切ったから、来月まで我慢」──こうしたルールを決めておくと、衝動買いを防げます。
6. 40代オタクのリアル:長く推すための備え
6-1. 体力・収入・時間の限界を意識
無理をすると「推し疲れ」や「金欠」で推し活自体が続けられなくなります。
6-2. 生活防衛資金は確保しておく
最低でも生活費の6か月〜1年分は貯蓄し、推し費は“余剰資金”で回すのが原則です。
7. 推しの卒業・結婚・炎上に備える?
何があっても「後悔しない」「生活が破綻しない」ように、推し活のお金は“流動性のある範囲”で使いましょう。
8. 「推しに恥じない推し活」を目指して
すべてを買うことが応援ではありません。
予算管理・優先順位付け・継続性を意識することで、「長く応援できるオタク」になれます。
まとめ
推しへの愛と、お金の現実。
この2つを両立するのは難しいようで、実は「ほんの少しの意識とルール」で可能になります。
推し活を、楽しく・健全に・長く続けていくために。
ぜひ、あなたの「推し費」も一度見直してみてください。
それでは今回はこのへんで。
また次の記事でお会いしましょう!
— シュンキャン

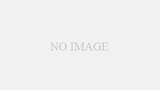
コメント